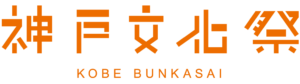「フラッガーズマーケット」は神戸文化祭フラッガー主催のチャリティバザーです。
神戸文化祭運営への資金援助と、フラッガーの交流の場として今年の5月から毎月第4土曜日に開催してきました。10月は本番目前ということで、同日夕方より前夜祭を開催いたします!できたてほやほやの神戸文化祭新聞もGETできますよ。11月の本番前にフラッガーとハンターが交流できる機会です。神戸文化祭ってなあにという方も大歓迎!どなたさまもお気軽にご参加ください。

神戸文化祭 フラッガーズマーケット&前夜祭
2023年10月28日(土)11:00〜
*フラッガーズマーケット
11:00〜17:00/入場無料
*フラッガーズマーケットカフェ
11:00〜17:00/料理人:ラ・ココット
旬のカフェランチ&スイーツでブレイクをどうぞ。
*神戸文化祭2023 前夜祭
17:00〜20:00/参加費:1,000円(1ドリンクとラ・ココットさんの軽食付き)
※準備の都合上、ご予約いただけると助かります。お名前と参加人数をnandemonaihi@kobebunkasai.clubまでお知らせください。